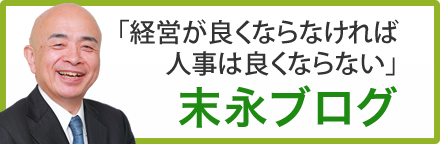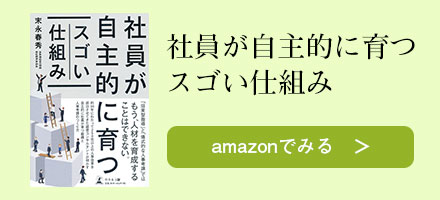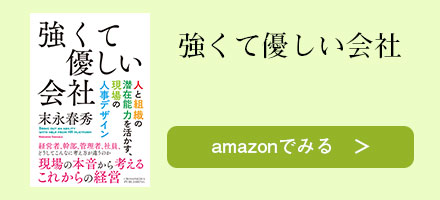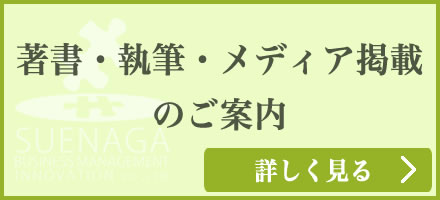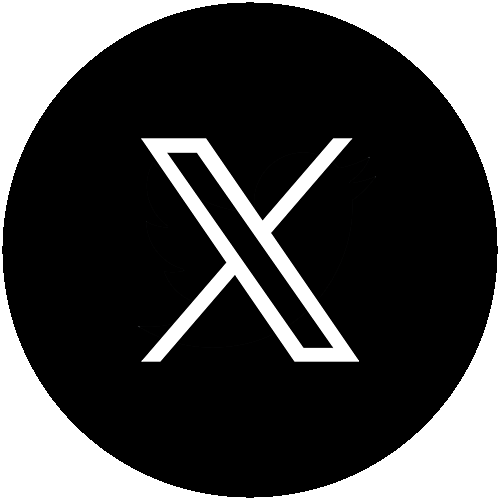末永ブログ

「静かな退職」が起きる職場の共通点|できる社員の意欲を取り戻す3つの打ち手
2025年11月10日
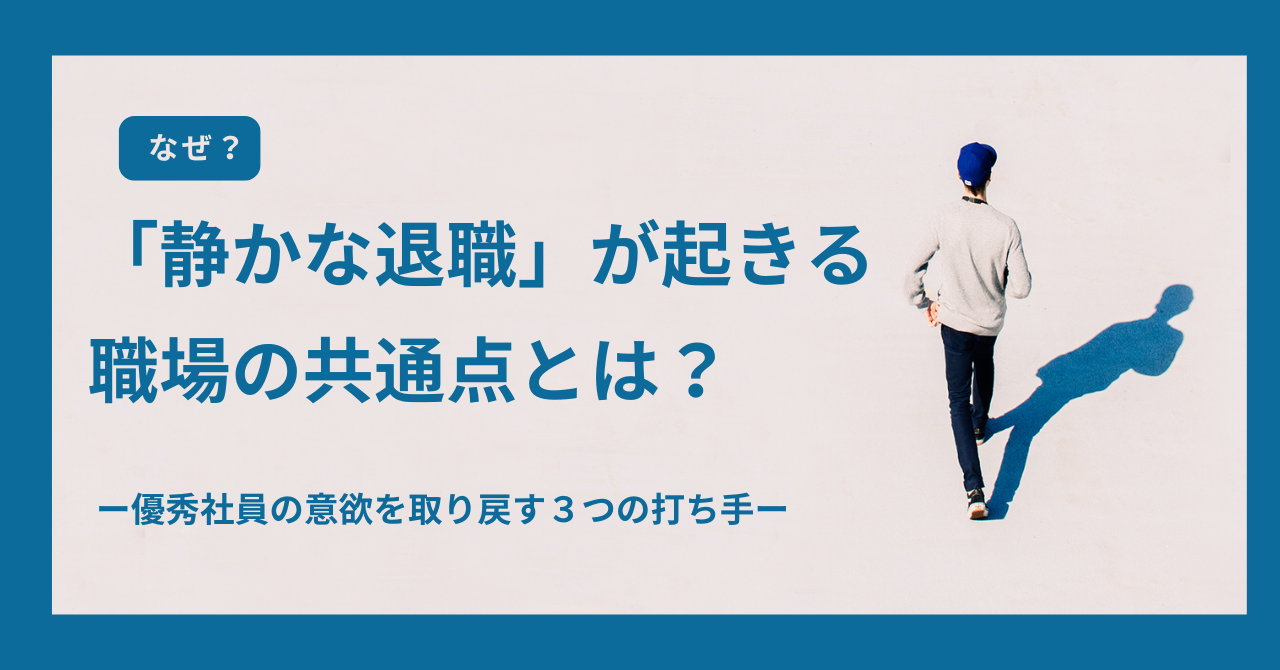
「辞めないまま、意欲が落ちる」という最大のリスク
近年「静かな退職(Quiet Quitting)」という言葉を耳にする機会が増えました。
退職こそしないものの、必要最低限の仕事だけをこなし、少しずつ関与を減らしていく――。この状態は“怠け”ではなく、むしろ多くの場合は、自分を守るための防衛反応なのです。
日本ではもともと従業員エンゲージメントが世界的に見ても低く、2024年時点で「熱意ある社員」はわずか6%という報告もあります。
さらに国内の別の調査では、「静かな退職」を経験した正社員が4割を超えるという結果もあり、特に若い世代ほどその傾向が強く表れています。
経営の現場にとって怖いのは、「辞めること」そのものよりも、辞めないまま意欲が失われていくことです。
そしてその上がらないモチベーションが周囲に波及します。静かに熱が冷めていくその過程で、周囲の士気や生産性にもじわじわと影響が広がります。
では、なぜこのようなことが起きるのか――。
ここからは、主な3つの原因と、それにどう向き合えばよいのかを、「対話」「評価」「職務設計」という3つのステップで見ていきましょう。
なぜ「静かな退職」が起きるのか――3つの構造的要因
① 努力が報われない構造
成果が見えにくく、評価があいまいな環境では、「どれだけ頑張っても同じ」と感じやすくなります。日本では“評価の納得感の不足”がエンゲージメント低迷と強く結びついており、この構造こそが“静かな退職”の温床になっていると考えられます。
② 責任だけが増える構造
人手不足や「できる人に仕事が集まる」状態が続くと、仕事ができる人ほど燃え尽きてしまいやすくなります。真面目な人ほど「辞める」という選択を避け、あらゆる関与を下げることでなんとか自分を守ろうとするのです。
ここで少し立ち止まって考えてみたいのが、「なぜ意欲の高かったできる社員ほど、燃え尽きてしまうのか?」ということです。
これは誰にとっても他人事ではないテーマです。主な要因を3つに絞って見ていきましょう。
﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌
▼できる社員が燃え尽き症候群に陥りやすい3つの理由
①「頼られすぎる構造」――“できる人ほど仕事が集まる”現象
成果が安定している人ほど、自然と依頼が集中します。周囲は「任せておけば安心」と思いがちですが、本人は「期待に応えたい」という責任感から断れず、結果として慢性的な過重負担に陥ってしまうのです。
②「評価が“当然化”される構造」――頑張っても“プラス評価”にならない
安定して結果を出す人ほど、その成果が“当たり前”と見なされやすい傾向にあります。「どれだけ頑張っても報われない」という感覚が積み重なり、「もう頑張らなくてもいいか」と気持ちが離れていってしまうのです。
これは、静かな退職の入口でもあります。
③「助けを求められない構造」――“弱音を吐けない優等生”の孤立
周囲からの信頼が厚いので、弱みを見せづらい立場になります。「自分が倒れたらチームが回らない」「自分だけ辛いとは言えない」――そうした孤立感と完璧主義が、ストレスを内面化させるのです。
さらに上司や経営層が「できる人だから大丈夫」と思い込むことで、フォローの網から漏れやすくなるため、疲弊が見過ごされやすいのです。
﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌ ﹌
なぜ「静かな退職」が起きるのか―3つの構造的要因の最後の一つは、対話が少なくなるその構造にあります。↓
③ 対話が細る構造
リモートワークや多忙な日々の中で、上司や同僚との関わりが減ると、心理的な距離も少しずつ広がっていきます。日本の”1on1″は普及が進んできたとはいえ、実際には制度化は約6割、ほとんどは「半年に1回程度の頻度」というデータもあり、「1on1の頻度と質」のばらつきが大きく、“本音を交わせる場”が足りていない現実があります。
また、その1on1自体の内容もパターン化してしまっているケースもよく見受けられます。
ここで大切なことは、「静かな退職」は本人の怠けではなく、モチベーション設計の問題だということです。
サインを正しく受け止め、環境を整えていけば、意欲は戻ってくるのです。
では、これらの要因をどう乗り越えて改善していくべきなのでしょうか?
具体的に説明していきます。

実践ステップ①:対話を定例化する――“沈黙”を可視化する設計
沈黙の増加(発言・雑談・相談の減少)は、もっとも早く出るSOSのサイン”です。これを見逃さず、早めにキャッチする仕組みづくりが大切です。
◆やること(設計図)
・週1回のミニ1on1(10〜15分)を導入:評価面談ではなく、「雑談+相互確認」を目的にします。
・質問を用意:
「仕事で今いちばん楽しいこと/難しいことは?」「どの業務を手放せたらパフォーマンスが上がる?」「3週間後、達成していたい“小さなゴール”は?」
このとき、上司の考えも伝えること。そして会社や部門のこと、仕事の意義を伝えることも重要です。
・対話を記録して管理する:懸念や支援要請を管理すること(例:負荷/キャリア/関係性)
・管理職側の研修:共感的傾聴・リフレーミング・事実と解釈の分離を習得。
◆根拠の補強
1on1は導入率こそ上がりましたが、頻度が成果に相関するとの報告があり、「月1回以上」の接点をもつほど目標達成度が高まる傾向が示されています。
また、エンゲージメントの高い企業は離職率が下がり、業績も向上するという知見が累積しており、対話投資は費用ではなく成長施策と認識するべきです。
◆現場のつまずき/回避策
・形骸化してしまう:アジェンダの固定化を避け、3回に1回はフリーテーマにしてみましょう。
・忙しくて時間が取れない:短時間・高頻度を徹底すること。10分でも“毎週”が効きます。
・本音が出ない:上司の自己開示から始める(失敗談・最近の学びを先に共有)ことで、場をほぐしてみましょう。
実践ステップ②:評価制度を見直す――“熱意”が報われる仕組み
静かな退職のコアは「報われなさ」にあります。成果以外の貢献(チームワーク・改善提案・学び)を評価に織り込み、「見てくれている感」を制度で担保します。
◆やること(設計図)
・短期フィードバックを標準化(年1からの脱皮)
・スポット表彰の運用:Slackなどのチャットや社内報で“いい仕事”を即時称賛。
◆根拠の補強
エンゲージメントが低いままでも我慢して働き続けるという構図が広がってしまうことで、「静かに距離を置く」行動に接続しています。
また国内調査では静かな退職経験者が4割超に達し、そのきっかけが「処遇・評価への不満」があると示されています。
「見られていない/報われない」感情への対処が急務になっているのです。
◆現場のつまずき/回避策
・評価者のバラつき:評価者の観点合わせを評価前に必ず定期的に行う。
・定性的評価の見直し:事例メモを本人・上司双方で平時から蓄積する。
・運用負荷:初期はスポット的な承認と定期的面談の二点だけに絞って着手することで、続きやすくなります。
実践ステップ③:職務設計を明確にする――“なんとなくの追加業務”をなくす
中小企業・成長企業ほど、善意の“ついで仕事”が積み上がり、責任だけが重くなる罠に陥ります。職務の棚卸と再設計で、安心して任せられる環境にすることが肝要です。
◆やること(設計図)
・業務棚卸ミーティング(隔月):各自が「開始・停止・継続」リストを共有してみる。
・職務・役割分担表を更新:誰が決めるか/誰が実行するかを明記。
・負荷の可視化:レッドゾーンの共有。
◆根拠の補強
「仕事量を減らし、重要業務に集中する」
生産性に対するこの考え方は、燃え尽きを避け、質を高めるアプローチとして注目されています。優先順位の明確化と上司との透明な合意形成が、静かな退職の予防線になります。
◆現場のつまずき/回避策
・“やれる人に集まる”:業務を任せる設計などをあらかじめ定義しておくこと
・棚卸が形骸化:取りやめること・その件数をあえて追う。

まとめ――“静けさ”は、組織が変われるチャンス
静かな退職は、個人を責める話ではなく、環境を見直すためのアラートと捉えて、チーム内や組織内で再設計していくことが大切です。
・対話で早期にサインを見つけ出し、
・評価でモチベーションを取り戻し、
・職務設計で無理なく力を出せる舞台を整える。
国内でも静かな退職が急増している今、決して他人事ではないと感じています。
ただし裏を返せば、”仕組みの着眼点”を変えれば”意欲を回復できる”ということです。
エンゲージメントが上がれば、離職は下がり、成果も上がる――これは日本の組織に必要な好循環です。そしてその改善には制度の再設計と現場の対話の両輪が必要です。
ここまでご覧いただきありがとうございます。