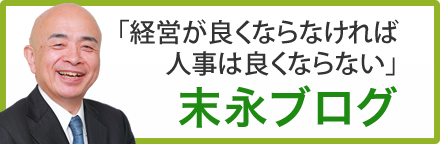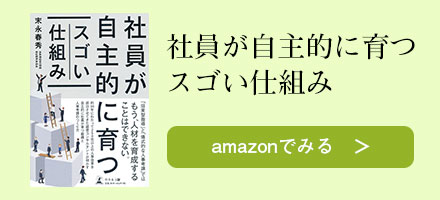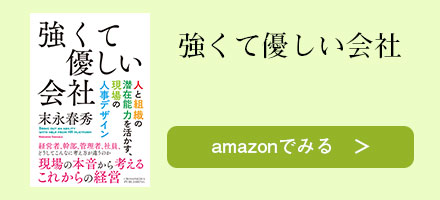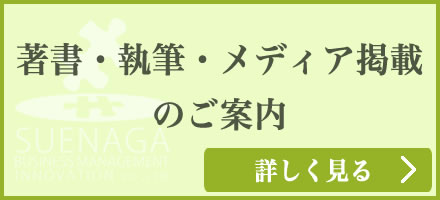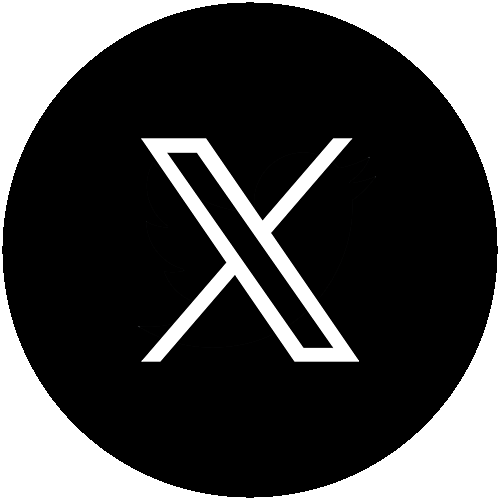末永ブログ

【経営者が選ぶ!】いま”管理職”が読むべきオススメ本4冊
2025年9月10日
こんにちは!広報のよっちゃんです!
弊社は、人事制度・組織作り、人材育成研修、業績改善・経営サポートを中心とした経営コンサルティング会社です。
今回、約30年以上コンサル業界で活躍する弊社の代表に、”ある質問”をしてみました…👇
ーーー社長、今の時代ビジネススキルをインプットできるツールって沢山ありますよね。
代表末永:「本当に便利になったね。」
ーーー結局、何を使うのが一番ですか?情報収集・学習できるアプリやデジタルツールがあり過ぎるんです。
”今の自分に最適”なものって何か…時間も限られているなかで無駄にしたくないんです。
代表:「やっぱり”本”でのインプットを薦めるよ。遠回りのように思えて、もっとも力が付く手段だと思う。
もちろん、何をどのように学びたいかで変わるけれど…YouTubeやオンライン学習できる動画ツールなども素晴らしいし、導入部分の理解や概要を掴んだりするのにはとても有効だし便利だね。あと、その人に合う合わないものは確かにある。
ただ、ビジネスの根幹をなす思考力や判断力を養うためには、やっぱり本を通じた深い理解、そして体系的で網羅的な学習が不可欠だと思うんだ。
そして何より、情報の質が高く、信頼性ある良書を選択するという技術も必要だね。」
「そこで得た知識や洞察で、キャリアを次のステージへと導いた人をたくさん見ているよ。」
ーーーなるほど…社長は今までどれくらい本を読んだんですか?
代表:「うーん、数千冊は読んでるかな。」
ーーーえ?!そんなに?!
代表:「大した事ないよ。むしろ、その中で巡り合う言葉・情報というのが必ずある。それは自分の職業人生を一生支えてくれるものになるから。」
ーーーなるほど…自分でも探してみますが、読書家の社長のおすすめを教えて下さい!
今回は、マネジメントスキルをはじめとしたあらゆる能力の研磨が必要とされる「管理職」の人に向けておすすめ本を4冊ピックアップ。
ベテランから若手管理者まで、為になる必読書です!
1.「成功への情熱」
著者:稲盛和夫/出版社:PHP研究所
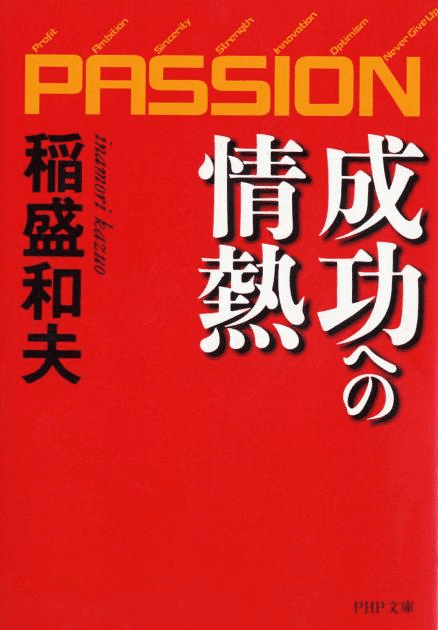
ーなぜ、あの人は組織を動かせるのか?
「言いたいことが部下に伝わらない」
「リーダーとして頑張っているのに、なぜか部下がついてこない」
「メンバーの心を一つにまとめたいが、どうすればいいか分からない」
多くの管理職が直面する悩み。その原因は、いったいどこにあるんでしょうか?
こういった課題の根底には、そのリーダーの情熱が「個人の情熱」に留まっていて、チーム全体に共有されていないという”問題”が潜んでいます。
京セラやKDDIを創業し、日本航空を再建した稲盛和夫氏が実践してきた経営哲学。それは、単なる組織運営のノウハウではなく、「人間として何が正しいか」という根源的な問いに基づいています。
管理職として、時には厳しい判断を下さなければならない場面でも、この本が示す「チームを動かすための人間的な力」を学ぶことで、迷いを断ち切る羅針盤となるのです。
部下との対話で「なぜこの仕事をするのですか?」と問われたときに、単なる業務目標ではなく、より大きな志を語れるようになる。その姿を部下は意外に見ているものです。
本書は、部下の心に火をつけ、共通の目標に向かって自律的に動くチーム・組織をつくるためのヒントを与えてくれます。
論理だけでは人は動きません。部下を論理で説得するのではなく、心の底から共感と信頼を獲得していくリーダーを目指したくなる一冊です。
2.「やり抜く力 GRIT」
著者:アンジェラ・ダックワース/出版社:ダイヤモンド社
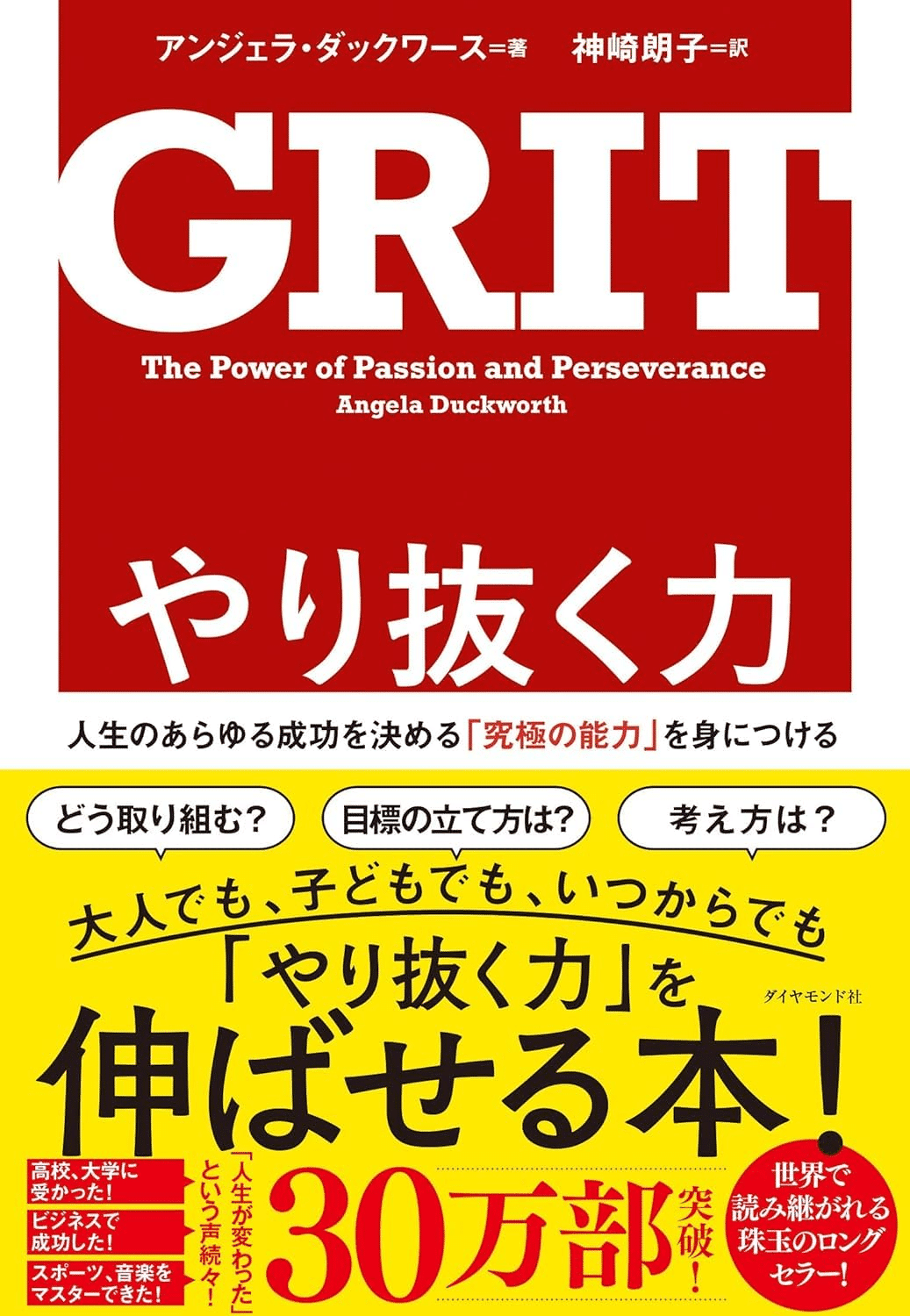
ー部下の才能を「やり抜く力」に変える方法
「部下のモチベーションが続かない」
「目標達成への執着心が足りない」
こういった「部下の能力をどう引き出すか」という課題は、管理職にとっては永遠のテーマでしょう。
では、どう能力を引き出していけばいいのか?
心理学者である著者は、才能やスキルといった先天的なものではなく、「やり抜く力(GRIT)」こそ重要なカギとなり、後天的に伸ばせる力だということを断言しています。
本書では、その”やり抜く力”を構成する要素を科学的に解き明かし、それを部下に育むための具体的な方法論を提示しています。
例えば、単に「頑張れ」と言うのではなく、部下が心から「興味」を持てる目標設定の方法や、失敗を成長の機会と捉えさせる「マインドセット」の醸成方法など、明日から実践できるスキルが満載です。
部下の能力を最大限に引き出し、チーム全体の生産性を飛躍的に高めることができるヒントがたくさん詰まっています。
3.「リーダーを目指す人の心得」
著者:コリン・パウエル/出版社:飛鳥新書
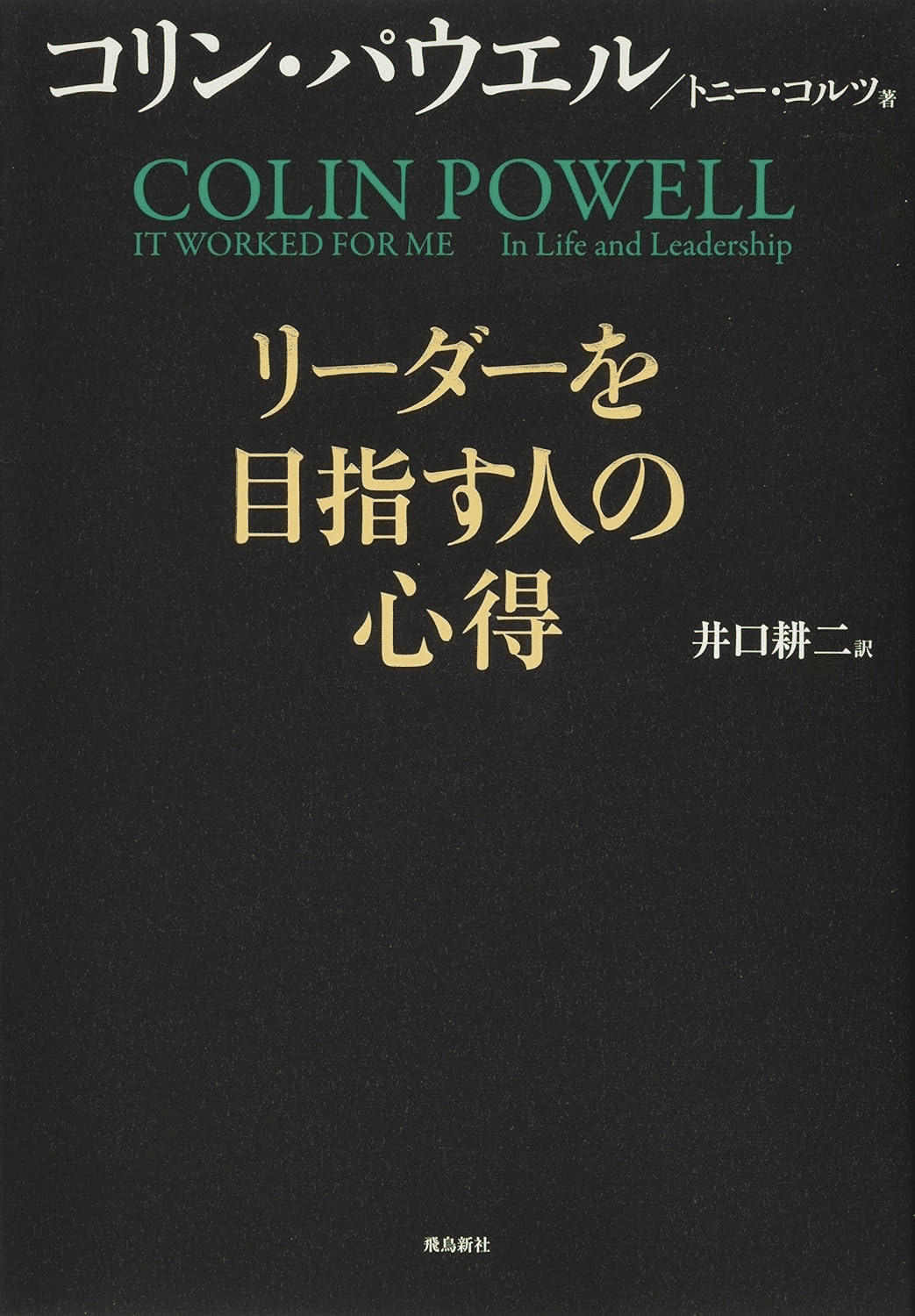
ーリーダーシップに悩んだら読む「辞書」
「部下との間に壁を感じる」
「どうすれば、もっと信頼してもらえるだろうか」
部下との間に発生しがちな”人間関係の悩み”に、この本は真正面から向き合い、答えを導いてくれます。
ペプシ工場の清掃夫から国務長官にまで上り詰めた米国史上屈指のリーダー、コリン・パウエル氏は、自身の壮絶な経験から「リーダーシップとは、権威ではなく”信頼”で成り立っている」と言います。
部下との間に信頼関係がなければ、どんなに優れた指示も意味を成さないのです。
全米で「最強のビジネス書」と言われたベストセラーである本書。
部下を管理する立場から、部下から信頼される真のリーダーへとステップアップするための”心得”や、組織内で昇進するための正攻法、人の心をつかむルールなど、参考になる知識が詰まっています。
リーダーのみならず、組織に身を置くすべてのビジネスパーソンに役立つ1冊です。
4.「樅の木は残った」
著者:山本周五郎/出版社:新潮文庫
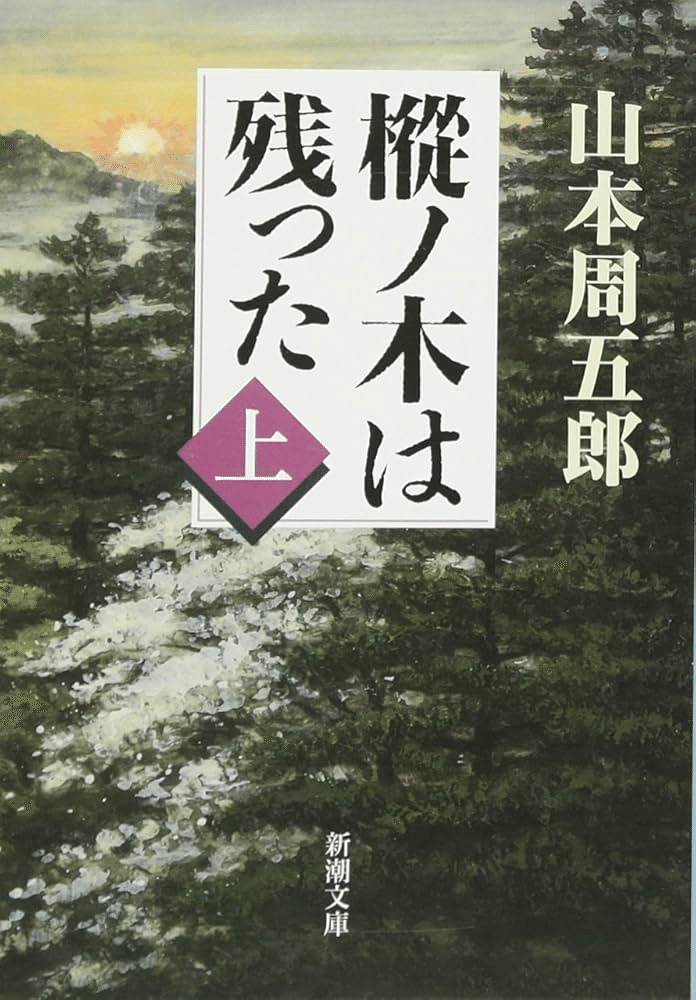
ーなぜ「ビジネス書以外」を読むべきなのか?
「なぜ、こんな理不尽な状況に直面しなければならないのか」
「組織の理不尽な論理と、部下を守りたいという信念の間で板挟みになる」
人間関係の駆け引きの中で、無力感を感じたことがある人も多いはず。現代の管理職もよく直面することだと思います。
江戸時代に仙台藩伊達家で起こったお家騒動「伊達騒動」を題材にしたこの物語。
権力争いの渦中にいながらも、自身の信念を貫こうとする一人の男性の姿を描きながら、”組織の論理”と”個人の信念”をどう両立させるかという永遠のテーマを問いかけます。
ビジネス書だけでは決して到達できない視点から、リーダーとしての覚悟や振る舞いを学ぶことができます。理不尽な状況でも、いかにして信念を貫き、部下を守るか。この本を読むことは、単なるインプットではなく、管理職としての「覚悟」を養う精神的なトレーニングとなります。
単なる歴史の知識を得るだけでなく、「組織の中での自分」というテーマを深く考えるきっかけになるのです。論理やデータだけでは乗り越えられない壁に直面したとき、人としてどうあるべきかという覚悟を養い、複雑な人間関係を読み解くための洞察力を磨くことができるでしょう。